 こんな落書きをつくってみました。TEDxKyotoのミーティングに行けなかったのでグレてます(そんなことありません)。だからRSAnimateっぽく書いてみました。
こんな落書きをつくってみました。TEDxKyotoのミーティングに行けなかったのでグレてます(そんなことありません)。だからRSAnimateっぽく書いてみました。番人たちのことはもういい。はやくレモネードみたいにニュースで乾杯(toast)できるように策略します。同志、求ム!
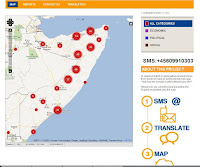
今年の初め、僕は自分が語ろうとしているものの呼び名がわからないということに気づいた。僕が語ろうとしているのは―ジャーナリズムにソーシャルメディア、サーチエンジン、図書館、それにウィキペディアとアカデミアなもの、これらを知識とコミュニケーションのシステムとして捉えたもの―呼び名はない。でも生態系が存在している。ツイッターからキュレートされたリアルタイムのフィードや、リファレンスとしてのウィキペディア、ニッチな最前線で活躍する記者たち、コンピューター科学者がその中にいて、人間とアルゴリズムの両方のキュレーターがいる。芸術家や芸術作品もそこにはあって、なんていうかみんなでシェアしている世界っぽいもの。
これを何て呼んでいるか、ある人は「メディア」だと答えたが僕はメディアの芸術性やエンターテイメントな側面を語ろうとしているわけじゃなく、もっとディスカッションとかコラボレーションを通じた調査、新しい知識がで生まれるような概念も含んだものを語りたいのだ。別の人は「インフォメーション」と呼んだけど、知らされる情報だけでは片付かない。すごく近いけど「第四の権力」が表す新聞やジャーナリズムだけじゃなく、市民参加やパブリックディスコースを含めた、民主主義の下にあるもの。
ひっくるめて、僕はこれをハバーマスの考えを下地にして「デジタルパブリックスフィア」と呼ぶことにした。ちょっとドライな名前になってしまったけど今のところはこれがベストに思った。Michael Shudsonの「ニュースが民主主義のためにできる6つか7つのこと」という論文からもインスピレーションを受けて、デジタルパブリックスフィアは僕たちのためになにができるか、を三つのまとめてみた。
1)情報
2)共感
3)コレクティブアクション
このコレクティブアクションというのは、共同体がオーバーラップする時代だから。
なんでこんなことを今話しているかって?ジャーナリズムにソーシャルメディア、サーチエンジン、図書館、それにウィキペディアにいろいろ・・は今こそ共通の目的のために協力しなくちゃいけないからだ。
今あるネットワーク化された非中央集権的な生態系が形作るデジタルパブリックスフィアをみんなが大事だと思える目標のために協力していこう。
SELECT * FROM parcels WHERE
ST_DWithin(geom, geomfromtext( 'point(-95.9375,41.2586)),.25);
nearby=Parcel.objects.filter(geom_distance_lte=(parcel.geom, D(mi=.25)))
(概要)
「ウェブVS紙媒体、ブロガーVSジャーナリスト、市民VSプロ」の議論はもう終わった。もはや区別など存在しない。今起きている最高のジャーナリズムはプラットフォームやプロセスに縛られていない。情報を広げ、自由にするために行われているのだ。このセッションでは「ニュース」の古い定義から飛び出し新しいあり方へ向かわせているジャーナリスト、新しい方法でストーリーを伝え、かつてジャーナリズムそのものがプラットフォームだった頃とは違い、ニュースをネットワーク的なアプローチで発展させているジャーナリストを迎える。ニュースを再発明し革新するマルチメディアジャーナリストの話を聞く。
2012年の大統領選にソーシャル・デジタルメディアはどんなトレンドを生みだすだろうか?Rock the Voteキャンペーンのような草の根の運動から何を今日に生かすべきか。クレイグリストのCraig NewmarkやRock The Voteの代表、PBSニューズアワー、VOTE LATINOよりスピーカーを迎える
公職選挙法でブログが書けない・・・とか言っている国にいると泣けてきますね。凍りつきます。ロボットとオタクと首相交代の国なのに・・・あ、だからか・・・。
 was founded in 2006, aims to eliminate violence against women, and promote women's right, peace and justice, through taking on issues such as comfort women and domestic violence.
was founded in 2006, aims to eliminate violence against women, and promote women's right, peace and justice, through taking on issues such as comfort women and domestic violence.